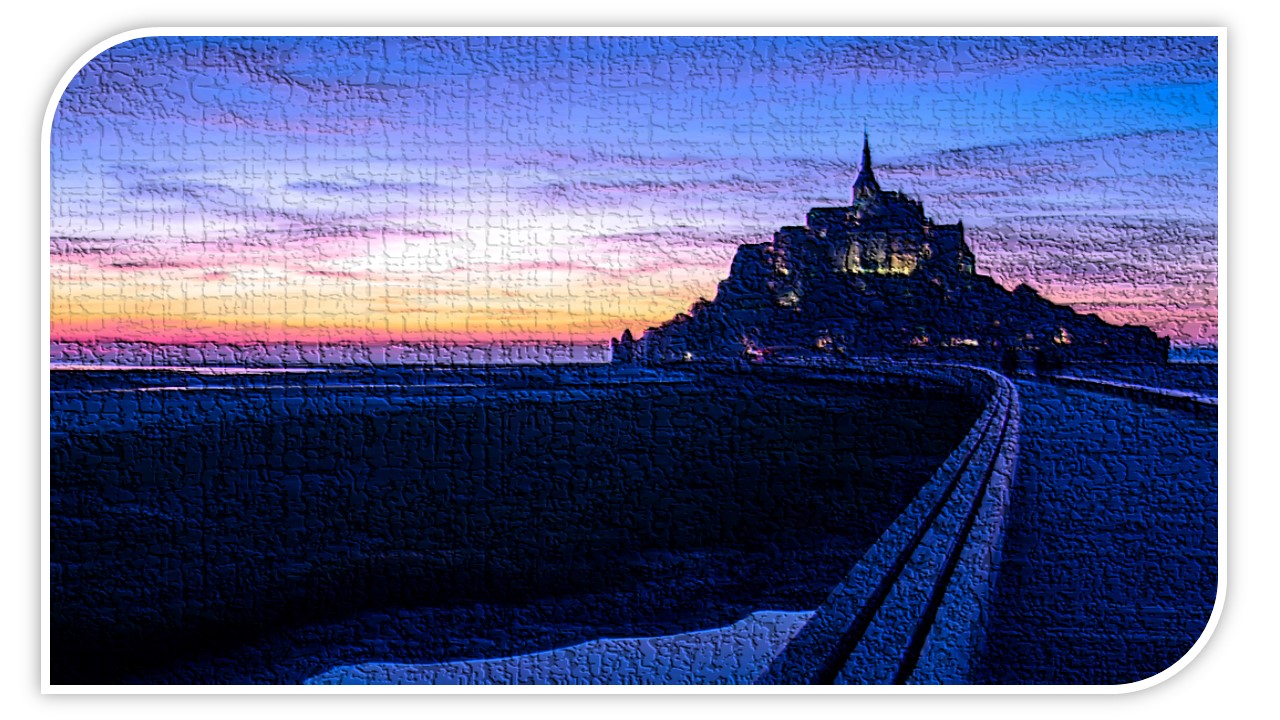屋上にあったのはぼくらのすべてだった
優越感とメロンパンを飲み込んで
ギターと終わらない歌で空に放った影
春と冬に境界なんかなく
秋だけは少しぼくらを遠ざけた
ごみ袋から吸い殻の匂いがむせ返って
やっと正気を取り戻す
なんてことをしてしまったんだ
もうハズカムの手には負えなかった
かと言ってグレートデーンなんか呼ぶほどでもない
炙ってから甘く煮付けた鮞の粒を
数え終わるまでに事は済む
先生は湯割りをひとくち啜り
最後の塊を箸で口に運んだ
奥歯の奥に逃げ込んだ数十粒を辛口が追い回す
先生が口籠るのはもちろん
なくならない死骸の心地悪さからで
煙草の臭いのする制服が見つからないためじゃない
そう信じれば裸足の理不尽さも
正当化ないし錯覚できたあれは暑い夏の真昼
ーendー